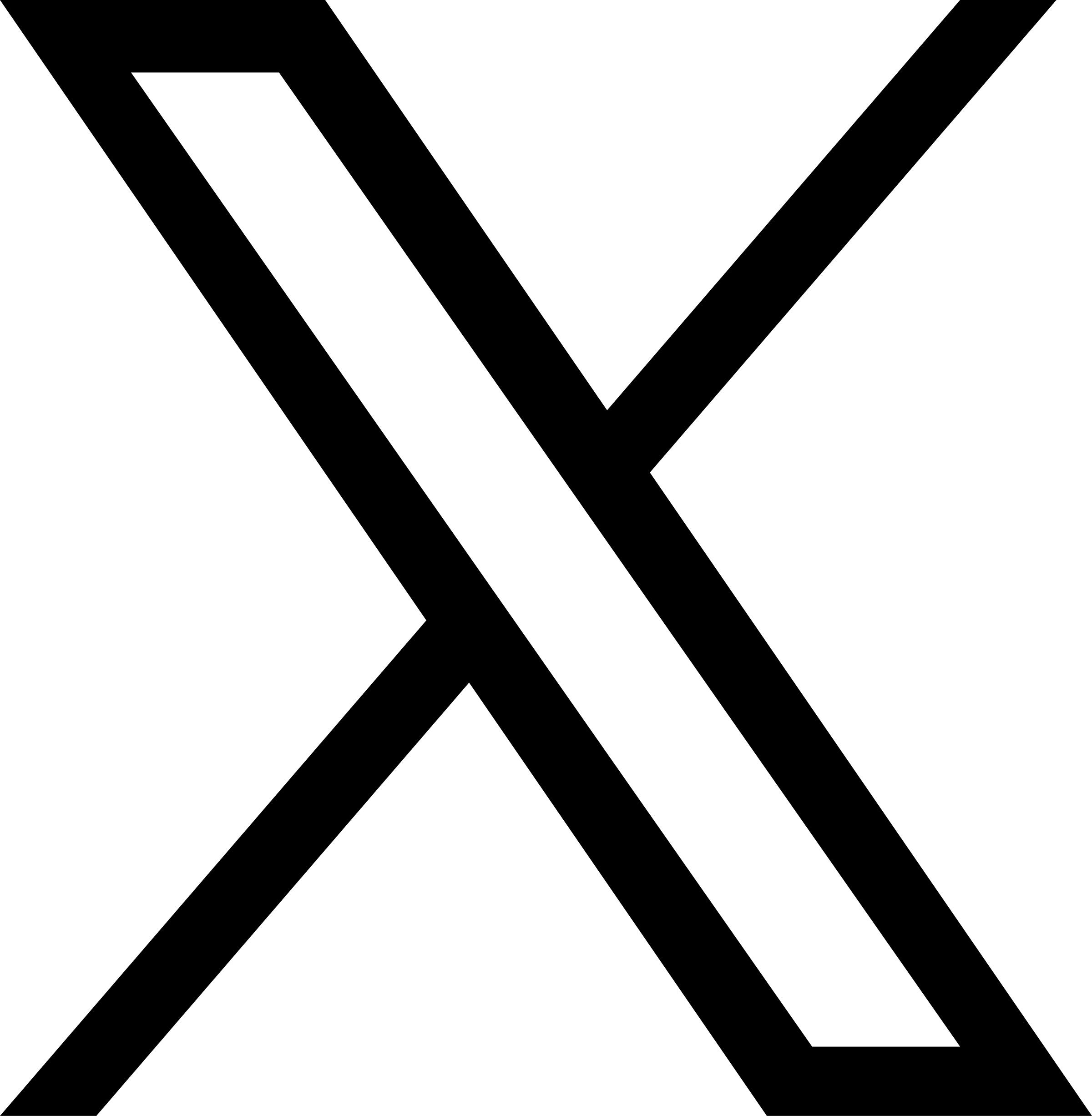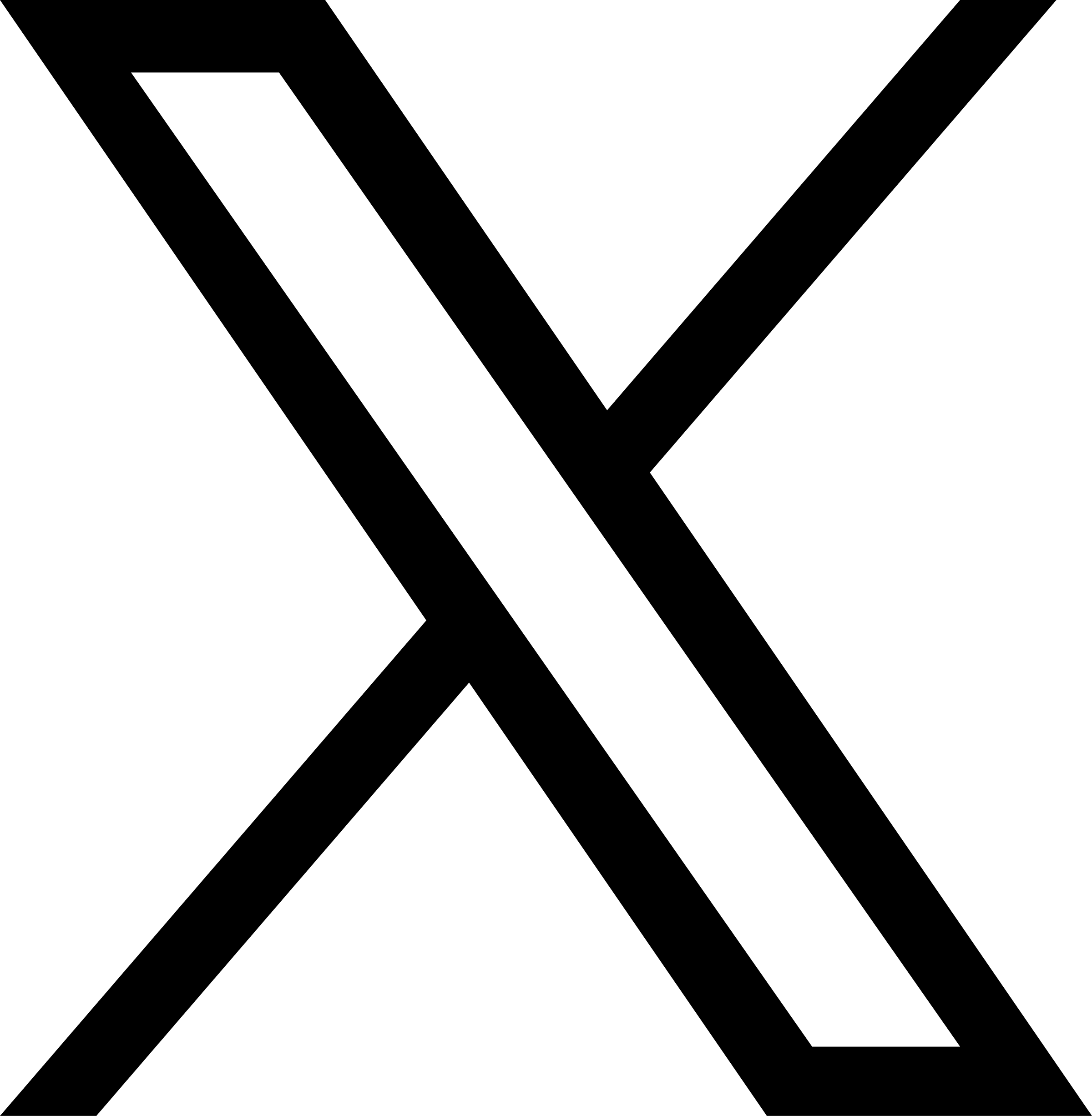就労移行支援事業所で給料はもらえる?制度の仕組みと活用法を解説
就労移行支援事業所で「給料」はもらえるのか――制度のしくみや支援内容に不安や疑問を感じている方へ。この記事では、工賃と給料の違い、利用によるメリット、注意点までをロジカルに解説します。制度を正しく理解し、自分らしい働き方への一歩を踏み出しましょう。

就労移行支援事業所とはそもそも何か
障がいや精神疾患を持つ方にとって、一般就労までの道のりは決して平坦ではありません。そうした現実を背景に整備された制度のひとつが「就労移行支援事業所」です。この支援は、日常生活に一定の支障を抱えながらも、働く意欲を持つ方が、安定した就労を目指すためのステップとして活用されています。
就労移行支援事業所は、障がい者総合支援法に基づいた福祉サービスの一環です。主な目的は、一般企業への就職を希望する利用者が、職場で求められるスキルや習慣を身につけられるように支援することです。支援内容には、パソコン操作やビジネスマナーの習得、履歴書の作成支援、模擬面接といった就職活動の準備が含まれます。また、生活リズムの安定や対人スキルの向上も、継続的な支援の中で重視される要素です。
この制度は、あくまでも「就職に向けた訓練と支援」であるため、働く場そのものを提供するわけではありません。そのため、就労の成果に対して直接的な「給料」が支払われる場ではなく、訓練を通じたスキル獲得が主眼に置かれています。
利用対象者とその要件とは?
利用できるのは、65歳未満で、身体・知的・精神のいずれかの障がいを持つ方、または発達障がいのある方などです。精神疾患の場合は、医師の診断や意見書が必要とされることが一般的です。また、障がい者手帳の有無だけで利用が決まるわけではなく、市区町村の相談支援専門員によるアセスメントを経て、サービス等利用計画が作成されます。
さらに、「就職を目指している」という明確な意欲があることが前提となります。たとえば、すでに長期間就労していない方でも、支援を通じて社会復帰を望んでいる意思があれば、対象に含まれる可能性があります。
利用期間と支援内容とは?
原則として、利用期間は最長で2年間とされています。この期間内に、段階的な支援を受けながら一般企業への就職を目指していく流れです。初期段階では、日常生活の安定やコミュニケーションの練習といった基礎的な支援が中心になります。その後、職業訓練や実習といった実践的なステップに進んでいくことで、就労に必要な準備を整えていきます。
支援内容は、事業所によって特色が異なります。たとえば、パソコンのスキル習得に力を入れている事業所や、対人関係のサポートに重点を置くところなど、個別性の高い支援が展開されています。利用者は、自分の状況や希望に応じて適切な事業所を選ぶことができます。
さらに、多くの事業所では企業見学や職場体験といった外部との接点も重視されています。こうした機会を通じて、現場の雰囲気を知ることができ、就職への具体的なイメージを持つ助けとなります。
就労移行支援事業所で得られる「工賃」とは?給料とは違う?
就労移行支援事業所を利用する際、多くの人が関心を持つのが「金銭的な報酬があるのか」という点です。この疑問に対して理解しておきたいのが「工賃」という概念です。工賃は、就労移行支援の中で特定の条件下で支払われることがあり、給料とは性質が異なります。
工賃の基本的な仕組み
工賃とは、訓練の一環として事業所内で取り組む作業に対して、一定の対価として支払われる報酬のことを指します。たとえば、軽作業やデータ入力、製品のパッケージ作業など、簡易的な業務に関わる場合に発生することがあります。ただし、工賃の支払いが義務付けられているわけではありません。すべての事業所が対象ではないため、工賃を期待して利用を始める前に、確認しておく必要があります。
この工賃は、あくまで職業訓練の一部として位置づけられているものであり、雇用契約に基づく「給料」とは制度的にも法的にも異なります。一般企業のような労働契約を結んでいるわけではないため、労働法に基づく賃金の扱いとはならない点が重要です。
就労継続支援との違い
工賃に関する誤解が生じやすいのは、「就労継続支援」と混同されるケースが多いためです。就労移行支援が「一般企業への就職を目指す訓練」であるのに対し、就労継続支援は「働き続けることが困難な方が、福祉的支援のもとで働く場を確保する仕組み」です。後者は実際に働くことが前提となっており、雇用契約や労働時間に応じて工賃が支払われる形となります。
一方、就労移行支援では訓練の一部として業務体験を行う場面もありますが、その活動に報酬が発生するかどうかは事業所の運営方針によって異なります。そのため、同じ「福祉サービス内の作業」でも、制度の違いによって金銭面の取り扱いが大きく変わる点に注意が必要です。
平均的な金銭的支援の傾向
就労移行支援で工賃が発生する場合、その金額は極めて限定的である傾向があります。支給額は地域、事業所の規模、業務内容などによってばらつきが大きく、一律ではありません。中には工賃が発生しない事業所も存在しており、支援の質や種類に重点を置いているケースもあります。
重要なのは、就労移行支援を「収入源」として期待するのではなく、「一般就労に向けた準備期間」として捉えることです。この期間中に安定した生活リズムを築いたり、職場で必要とされるスキルを身につけることが、長期的に見たときの収入向上につながる可能性があります。工賃は、その過程で得られる副次的な報酬として捉えるのが現実的です。
就労移行支援の制度は、金銭よりも将来の自立に向けた基盤作りを目的として設計されています。その本質を理解した上で、自分に合った支援環境を見極めることが、制度を正しく活用するうえで欠かせない視点となります。
就労移行支援事業所で給料がもらえる仕組みはあるのか?
就労移行支援事業所の利用を検討している中で、「給料を受け取ることができるのか」という疑問を持つ方は少なくありません。この問いに答えるためには、雇用契約の有無や支援内容の性質を理解する必要があります。
雇用契約の有無による違い
就労移行支援は、あくまで「一般企業への就職に向けた準備」を支援する制度です。そのため、利用者と事業所の間に雇用契約が結ばれているわけではありません。したがって、原則として給料は発生しません。給料は雇用契約がある場合に支払われる労働の対価です。就労移行支援事業所における活動は、就労に必要な知識や技術、生活習慣を身につけるための訓練という位置づけになります。
ただし、就労体験や企業実習の場面で、受け入れ先企業が一定の謝礼や奨励金を支払うケースも存在します。これらは給料とは異なる形式での支援であり、あくまで訓練の一環として提供されるものです。給与所得としての取り扱いには該当しないため、その点を理解しておくことが必要です。
企業との直接雇用につながる例
就労移行支援の大きな目的は、最終的に一般企業へ就職し、継続的な収入を得られるようになることです。そのため、多くの事業所では企業実習や職場見学を通じて、利用者と企業のマッチングを促す取り組みが行われています。この過程で、企業側が利用者の適性やスキルを評価し、雇用契約につながるケースもあります。
実際に就労が決まれば、雇用契約が締結され、給料が発生します。このような流れが実現する背景には、企業側が障がい者雇用に対する理解を深めていることや、支援機関が間に入って職場定着を後押ししていることがあります。事業所と企業、そして利用者の三者が連携を取りながら進めることで、実際の就職という成果につながる道が開けるのです。
就労実績とスキル習得の関係
給料を得るには、企業が求める一定のスキルや職業的な習慣を身につけることが前提になります。就労移行支援事業所では、利用者の特性や課題に応じて、段階的な支援が行われます。たとえば、時間管理や報連相、作業の正確性といった基本的なビジネススキルの訓練に加えて、対人関係の安定化を図るプログラムが取り入れられています。
こうした積み重ねが、将来的に企業からの評価につながり、採用へと発展していきます。最初は就職への不安や抵抗を抱いていた方でも、支援を受けながら着実に力をつけていくことで、実際の就労の場で必要とされる人材へと成長することが可能です。結果として、給料が発生する働き方へと移行していく道筋が見えてきます。
就労移行支援事業所に実際に通うとどんなメリットがあるのか?
就労移行支援事業所の利用を検討する際、多くの方が気になるのは「通うことによって本当に意味があるのか」という点です。給料や工賃の有無にかかわらず、この制度が提供する支援には金銭的なもの以外にもさまざまな価値があります。ここでは、就労移行支援事業所に通うことの具体的なメリットを3つの観点から見ていきます。
金銭面以外の価値
就労移行支援は、一般企業で働くための準備を整えることが目的です。そのため、通所を通じて得られる最大の効果は、生活リズムの安定と心身の調整です。毎日決まった時間に事業所へ通う習慣を持つことで、日常生活にメリハリが生まれます。これは将来的に就職してからの勤務継続に直結する重要な土台となります。
また、事業所ではスタッフや他の利用者とのコミュニケーションを通じて、対人スキルや協調性を高める機会も得られます。孤立しがちな状況から一歩踏み出すきっかけとして、社会的なつながりの形成が支援の大きな柱となっています。
職業体験や資格取得支援
多くの事業所では、訓練プログラムの一環として職業体験の機会を設けています。これは、就職活動に向けたスキルアップだけでなく、自分に合った仕事や職場環境を見極めるうえで有効です。実際に体験を通して働くイメージが明確になることで、就職に対する不安を和らげる効果が期待されます。
さらに、資格取得をサポートする取り組みも一般的に行われています。たとえば、パソコンの基礎操作やビジネスマナー、文書作成に関する研修を実施している事業所もあります。資格があることで応募できる求人の幅が広がり、企業からの評価にもつながります。これらの支援は、就職後の定着を見据えた包括的なアプローチといえます。
主要な就労移行支援事業所の取り組み
就労移行支援事業所は全国に数多く存在し、その運営方針や支援の特徴もさまざまです。中でも、LITALICOワークスやメルディアトータルサポートのように支援実績の多い事業所では、個別支援計画に基づいたきめ細かなサポートを行っています。これにより、障がい特性に応じた訓練内容の調整や、就職後の職場定着支援など、利用者の状況に応じた支援が受けられます。
これらの事業所では、利用者の自己理解を深めるプログラムにも力を入れており、自分の強みや課題を整理することによって、より現実的で納得感のある就職先選びが可能になります。就労後の不安を軽減し、長期的な働き方を実現するための後押しとして、実績ある支援体制は重要な要素といえるでしょう。
給料の注意点と事前に知っておくべきこと
就労移行支援事業所は、多くの障がいや精神疾患のある方にとって、一般就労への大きな架け橋となる支援制度です。一方で、利用するうえで事前に把握しておくべき点や、誤解を避けるための注意点も存在します。ここでは、制度を正しく活用するために確認しておくべき情報を紹介します。
工賃や収入への過度な期待を避ける
まず重要なのは、就労移行支援事業所の利用によって安定した収入を得られるという誤解を避けることです。制度上、就労移行支援では給料は支払われず、工賃が発生する場合でもその目的はあくまで訓練の一部です。経済的な自立を目的とする支援ではなく、将来的な就職に向けたステップであるという理解が必要です。
金銭的な報酬を前提として利用を開始すると、「想像していたものと違う」と感じる可能性が高くなります。そのため、利用前に制度の仕組みや支援の目的を正しく認識しておくことが大切です。
制度の利用期限と卒業後の進路を確認する
就労移行支援には、原則として最大2年間という利用期間の上限があります。この期間内に必要なスキルや知識を習得し、一般企業への就職を目指すのが基本的な流れです。ただし、やむを得ない事情がある場合には延長が認められるケースもあります。
また、就職が難しかった場合の選択肢として、「就労継続支援」や「生活訓練」といった他の福祉サービスへの移行が検討されることもあります。自分に合った進路を考えるうえで、卒業後の選択肢についても事前に知っておくと、安心して支援を受けることができます。
見学や相談を活用してミスマッチ防止を防止する
就労移行支援事業所は全国に多く存在しており、その支援方針や訓練内容には違いがあります。たとえば、事務職を目指す方にとってはパソコン訓練が充実している事業所が適している一方で、コミュニケーション支援に特化している事業所もあります。自分の目標や特性に合った支援が受けられるかどうかを見極めるためには、事前の見学や相談が欠かせません。
多くの事業所では、見学・体験利用の制度を設けています。また、市区町村の障がい福祉課や相談支援専門員を通じた情報収集も有効です。初めての利用であっても、必要な情報にしっかりアクセスし、自分に合った環境を選ぶことで、支援の効果を最大化できます。
事前の情報収集や相談は、支援を受け始めた後のミスマッチや不安を防ぐうえで重要なプロセスです。信頼できる支援機関と連携しながら、慎重に準備を進めることが、就労への第一歩につながります。
まとめ
就労移行支援事業所は、障がいや精神疾患を持つ方が一般就労を目指すうえで、現実的かつ実用的なサポートを提供しています。金銭的な報酬そのものを目的とする制度ではないものの、通所を通じて生活の安定やスキル習得、人とのつながりといった多面的なメリットを得ることができます。
「給料」というキーワードに惑わされず、支援の本質を理解したうえで活用することで、将来的な自立や職場定着の実現につながる可能性が広がります。制度の理解と事前の準備が、より良い就労への第一歩となるはずです。
就労移行支援についてもっと具体的に知りたい方、自分に合った支援環境を見つけたい方は、一般財団法人メルディア「メルディアトータルサポート」の公式ページをご覧ください。利用者一人ひとりに寄り添った支援で、あなたの就職活動を力強くサポートします。
初回相談や見学も受付中です。詳しくは公式サイトをご覧ください。公式サイトはこちらから→ https://mlda.jp/mts/