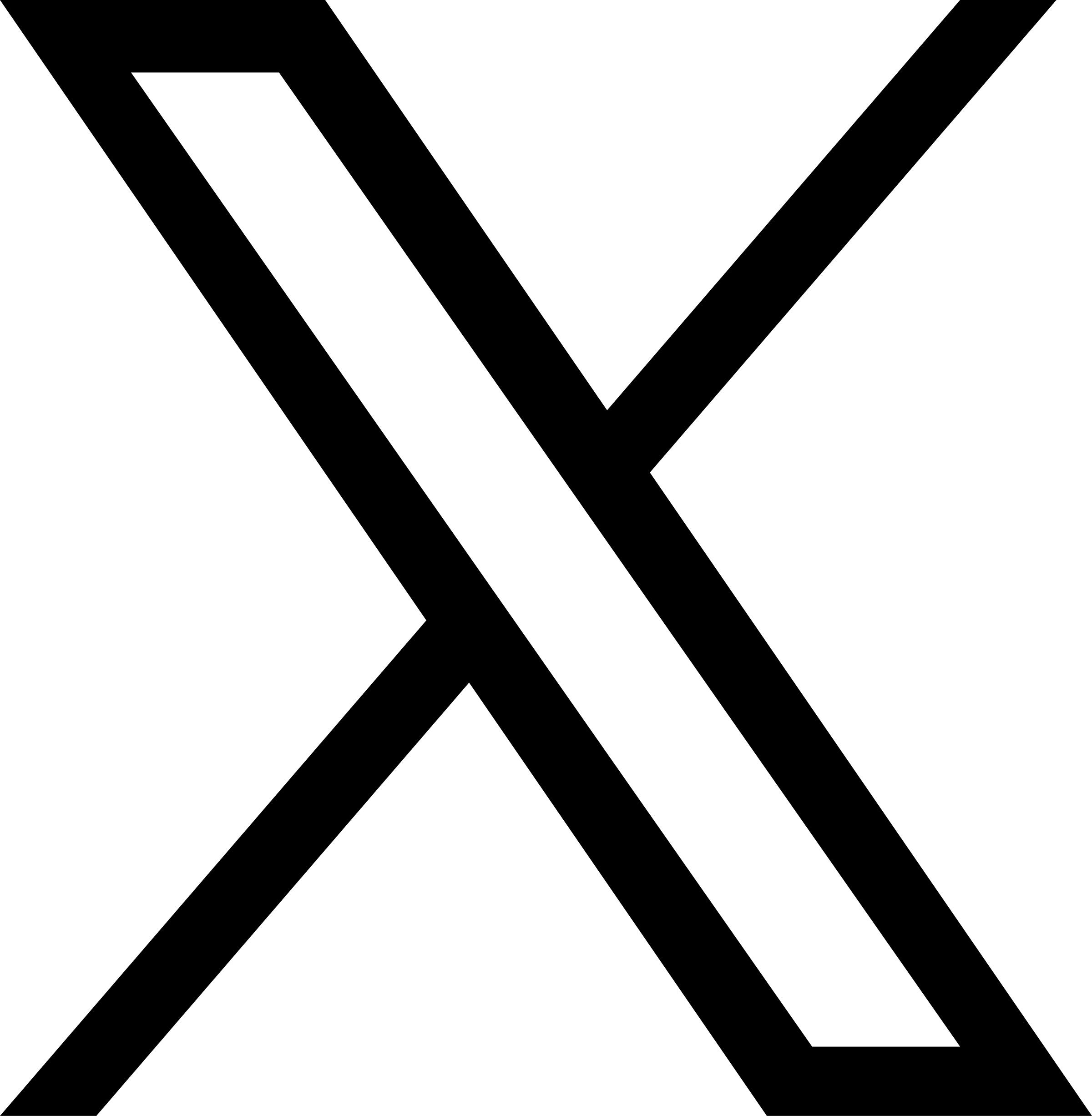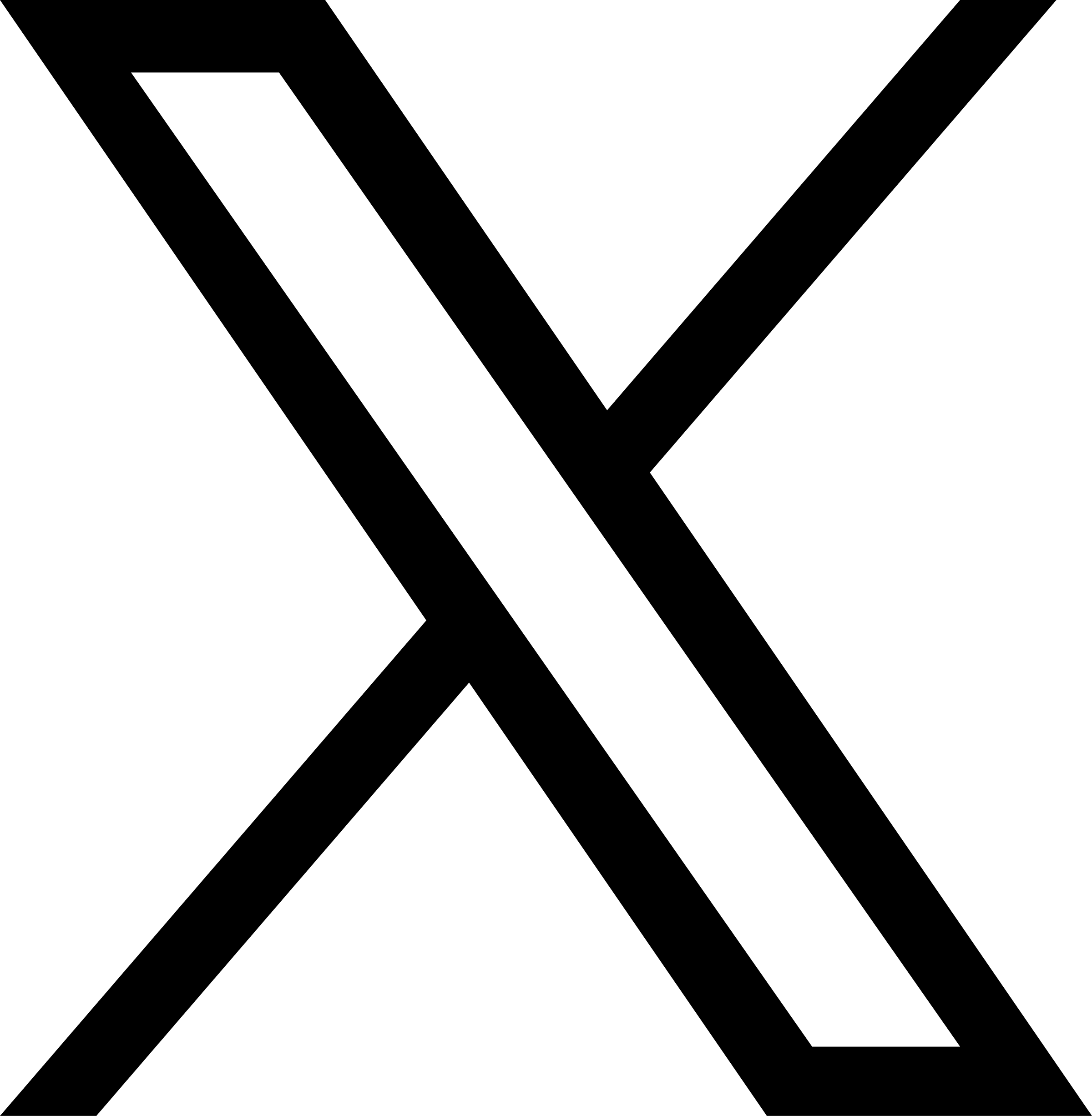就労移行支援事業所とは?就労継続支援の違いは?A型・B型の仕組みも徹底解説します
就労移行支援事業所やA型・B型の支援の違いを正しく理解することは、自分に合った働き方を見つけるための重要なステップです。本記事では、それぞれの支援の仕組みや対象者、選び方のポイントまでをわかりやすく解説します。

就労移行支援事業所とは何か?
働くことは、単に収入を得るだけでなく、社会とのつながりを築くうえでも大きな意味を持つものです。しかしながら、障がいや精神疾患をお持ちの方々にとっては、就職や職場の継続が大きな壁となることも少なくありません。そうした課題に対応するための福祉制度として「就労支援サービス」が整備されています。
就労支援サービスの目的は、一般就労が難しい方や、働く経験が十分にない方々に対し、適切な準備や機会を提供することにあります。生活リズムの安定から職業訓練、さらには職場への定着まで、段階を追って支える仕組みになっているのが特徴です。
このようなサービスは、本人の希望を尊重しつつ、無理のないステップで「働くこと」に近づけるサポートを行っています。そのため、働くことに不安を感じている方でも、少しずつ自信を取り戻しながら前に進める道筋を描けるようになっています。
就労移行支援と就労継続支援の位置づけ
就労支援にはいくつかの種類がありますが、特に利用者数が多く、制度としても重要なのが「就労移行支援」と「就労継続支援」です。それぞれの役割や対象者が異なり、支援の内容も明確に分かれています。
就労移行支援は、企業での一般就労を目指す方に向けた支援です。働くために必要なスキルや知識を身につけることを主な目的としており、職業訓練や履歴書作成、面接対策などが提供されます。この支援は、ある程度の就労可能性がある方が対象で、実際に一般企業で働くことをゴールとしています。
一方、就労継続支援は、現時点では一般就労が難しい方に対して、働く場そのものを提供する支援です。こちらはさらに「A型」と「B型」に分かれており、それぞれ雇用契約の有無や働き方に違いがあります。たとえば、A型は事業所と雇用契約を結んで働く形式であり、一定の就労能力が求められます。B型は契約を結ばず、ご自身の体調や生活リズムに合わせて働ける柔軟な支援形態になっています。
これらの支援制度は、単なる職業紹介にとどまらず、日常生活の安定や人間関係の構築にも目を向けています。支援の内容は多岐にわたりますが、最終的には「その方が自分らしく働き続けること」が共通の目標となっています。
例えばLITALICOワークスやメルディアトータルサポートのように、就労移行支援に特化しつつも、個別のニーズに合わせたプログラムを展開している事業所も増えています。自身にとって適切なサービスを選ぶことで、無理なく就労への第一歩を踏み出すことができるようになっています。
就労移行支援のしくみと対象者を解説
就労移行支援は、障がいや精神疾患を抱える方が一般企業への就職を目指すための制度です。この支援は、ただ単に仕事を斡旋するのではなく、「働く準備」を整えることに重きを置いているのが特徴です。
利用対象となるのは、障がい者手帳を持っている方や医師の診断を受けている方など、働くことに何らかの困難を抱えている方です。ただし、利用に際しては年齢や意欲といった要素も考慮されます。特に、65歳未満で「働きたい」という希望を持っている方が主な対象となります。
現時点で就職が難しいと感じていても、意欲があったら利用できる可能性があります。就労移行支援は、働く力を段階的に高めながら、社会への復帰を目指すための後押しとなるサービスです。
移行支援でできること
就労移行支援の中心となるのは、就職に必要な知識やスキルの習得です。具体的には、ビジネスマナーの研修、履歴書の書き方、面接対策などが提供されており、就労経験がない人でも安心してステップアップできる内容になっています。
また、職場実習や体験を通じて、実際の働く環境に慣れていくことも可能です。これは、机上の訓練だけでは得られない「実践力」を身につけるうえで非常に効果的です。さらに、利用者一人一人に対して担当の支援員が付き、キャリアプランの設計や相談にも応じます。
こうした支援を通じて、就職活動に向けた自信や自己理解を深めることができます。誰かに相談しながら準備を進められる環境が整っているため、不安を感じながらも一歩踏み出すための支えとなります。
LITALICOワークスやメルディアトータルサポートなどがこのような支援を提供しており、地域によってさまざまな事業所が展開されています。どの支援機関にも共通しているのは、「利用者の可能性を信じ、就職まで伴走する姿勢」です。
就労移行支援は、就職がゴールではなく、働き続けられるようになるまでを見据えた長期的な支援です。そのため、制度を活用することで、自分に合った働き方や職場環境を見つけることができる可能性が広がっています。
就労継続支援事業所のA型とB型とは?違いを解説
A型は雇用契約あり・B型はなし
就労継続支援は、障がいや精神疾患を抱える人が「働き続ける」ことを目的とした制度であり、A型とB型の2つに分類されています。これらの最大の違いは、雇用契約の有無にあります。
A型では、支援事業所と雇用契約を結んだうえで働くことになります。これは、形式としては一般の企業と同じで、出勤日数や勤務時間に応じた給与が支払われます。雇用契約があるということは、労働基準法などの適用も受けるため、一定の就労能力や安定した通所が求められます。
一方、B型では雇用契約を結ばず、より柔軟な働き方ができる仕組みになっています。支援の内容としては軽作業や内職的業務などが中心となり、自分の体調や生活リズムに合わせて働くことが可能です。無理なく、継続的に「働く経験」を積みたい人にとっては、有効な選択肢となりえます。
このように、A型はより”就労に近い”形、B型は”訓練と社会参加”を重視した形で設計されており、どちらを選ぶかは本人の状況に大きく左右されます。
A型、B型の対象者と働き方のちがい
A型とB型では、対象者の条件にも違いがあります。A型は、ある程度の就労能力があり、通勤や業務に一定の安定性があると判断された人が対象になります。生活リズムが整っていて、継続して働く意欲を持っている人には適しています。
それに対してB型は、今すぐには一般就労が難しい場合や、体調の波が大きい人などが対象となります。日によって働ける時間が異なったり、通所の頻度にばらつきがあるようなケースでも受け入れてもらえる環境が整っています。
働き方にも大きなちがいがあります。A型では出勤や業務内容に一定のルールがあり、職場内での役割分担や時間管理が求められます。一方でB型では、より自由度が高く、1日数時間だけ働くといった選択もできます。支援員のフォローのもと、自分に合ったペースで参加することが前提となっています。
A型・B型を利用するには?
就労継続支援A型・B型の利用を検討する際は、まず市区町村の窓口や専門の相談支援機関に相談することが一般的です。利用希望者は、相談を通じて自分の状態や希望を整理し、適切なサービスを選ぶためのアドバイスを受けることができます。
次に、支援事業所の見学や体験を行い、自分に合った環境かどうかを確認します。このステップでは、実際の作業内容や事業所の雰囲気、支援スタッフの対応などが重要な判断材料となります。
利用が決まれば、サービス等利用計画の作成や支給決定といった手続きを経て、通所が開始されます。この過程で、本人の希望や体調、生活環境に応じた柔軟な支援計画が立てられます。
A型・B型いずれにも対応している事業所が多数存在します。たとえば、LITALICOワークスやメルディアトータルサポートのような支援機関では、初期相談から利用開始後のサポートまで一貫して対応しているケースもあります。こうしたサポート体制を活用することで、より安心して支援を受けることができます。
自分にあった就労支援サービスを選ぶには?
就労移行支援や継続支援A型・B型のような制度は多様であり、どれが自分に適しているのか悩む人も多いです。支援を選ぶうえで重要なのは、「今の自分の状態」と「将来的にどんな働き方をしたいか」という2つの視点で考えることです。
たとえば、体調が安定していて就職を本格的に目指したい場合は、就労移行支援が選択肢になりやすいです。一方で、安定した勤務が難しい場合や、まずは生活リズムを整えたいと考えるなら、B型のほうが負担が少なく適していることもあります。
また、A型を検討する人は、「雇用される」という意識で取り組む覚悟が求められます。決まった時間に出勤し、責任を持って業務を行うことが前提となるため、自信の有無だけでなく、生活面も含めたバランスを見極める必要があります。
いずれの場合も、「自分に合った支援を選ぶ」ことが、長く無理なく働くための第一歩となります。焦らずに、段階的に選択肢を絞っていくことが大切です。
見学・体験利用を活用する
選び方に迷ったときに役立つのが、事業所の「見学」や「体験利用」です。これは、制度上も推奨されている手続きの一つであり、実際の支援内容や雰囲気を直接確認できる機会として活用されています。
実際に事業所を訪れることで、パンフレットやホームページだけではわからない空気感や、スタッフとの相性を感じ取ることができます。利用者がどのようなサポートを受けているのか、どのような作業を行っているのかを見学することで、イメージが具体化されやすくなります。
また、体験利用では短期間ながらも実際にプログラムに参加できるため、「通所できるか」「続けられそうか」といった現実的な判断材料が得られます。これは、形式上の理解だけではなく、自分自身の感覚と照らし合わせて選ぶうえで大きなヒントになります。
支援機関によって対応の丁寧さや雰囲気には違いがあるため、複数の事業所を比較することも有効です。実際の体験を通じて納得したうえで選ぶことで、安心して次のステップに進める土台ができあがります。
評判の高い就労支援事業所の例
全国展開している大手の支援機関から地域密着型の事業所まで、多様な選択肢が存在します。中でも、LITALICOワークス、ミラトレ、ウェルビー、そしてメルディアトータルサポートなどは、初心者にも利用しやすい体制と実績を持つことで知られています。
これらの事業所では、初回相談から見学、体験、利用開始後のサポートまでが一貫して提供されており、はじめて就労支援を利用する人にも負担が少ない仕組みが整っています。また、支援員が個別の相談に応じ、利用者の特性や希望に応じた支援計画を柔軟に立てていることも特徴的です。
特にメルディアトータルサポートは、障がいや精神疾患を持つ人の「働く力」を最大限に引き出すことに重点を置いており、個別支援やステップアップ型の支援プログラムなどを通じて、利用者一人一人が自分らしく働ける環境づくりに取り組んでいます。
初回相談や見学も受付中です。詳しくは公式サイトをご覧ください。公式サイトはこちらから→ https://mlda.jp/mtsinquiry/
このように、事業所ごとに提供されるサービスの方針やサポート内容には違いがあります。信頼できる支援機関を見つけることが、自分に合った働き方を見つけるうえでの確かな足がかりとなります。
まとめ
就労移行支援や就労継続支援A型・B型は、それぞれ異なる特性と目的を持ちながら、障がいや精神疾患のある人の「働く」を支える重要な制度です。自分に合った支援を選ぶには、制度の仕組みや対象者、働き方の違いを知ることが第一歩となります。無理のないペースで一歩ずつ進んでいくことで、将来の可能性を広げる道が見えてきます。
もし、どの支援サービスが自分に合っているのか迷っている場合は、一般財団法人メルディアが運営する「メルディアトータルサポート」のように、就労に向けた個別相談を受け付けている支援機関に相談してみてください。あなたに合った働き方を見つけるきっかけとなるはずです。まずは一歩、話してみることから始めてみませんか。
初回相談や見学も受付中です。詳しくは公式サイトをご覧ください。公式サイトはこちらから→ https://mlda.jp/mtsinquiry/