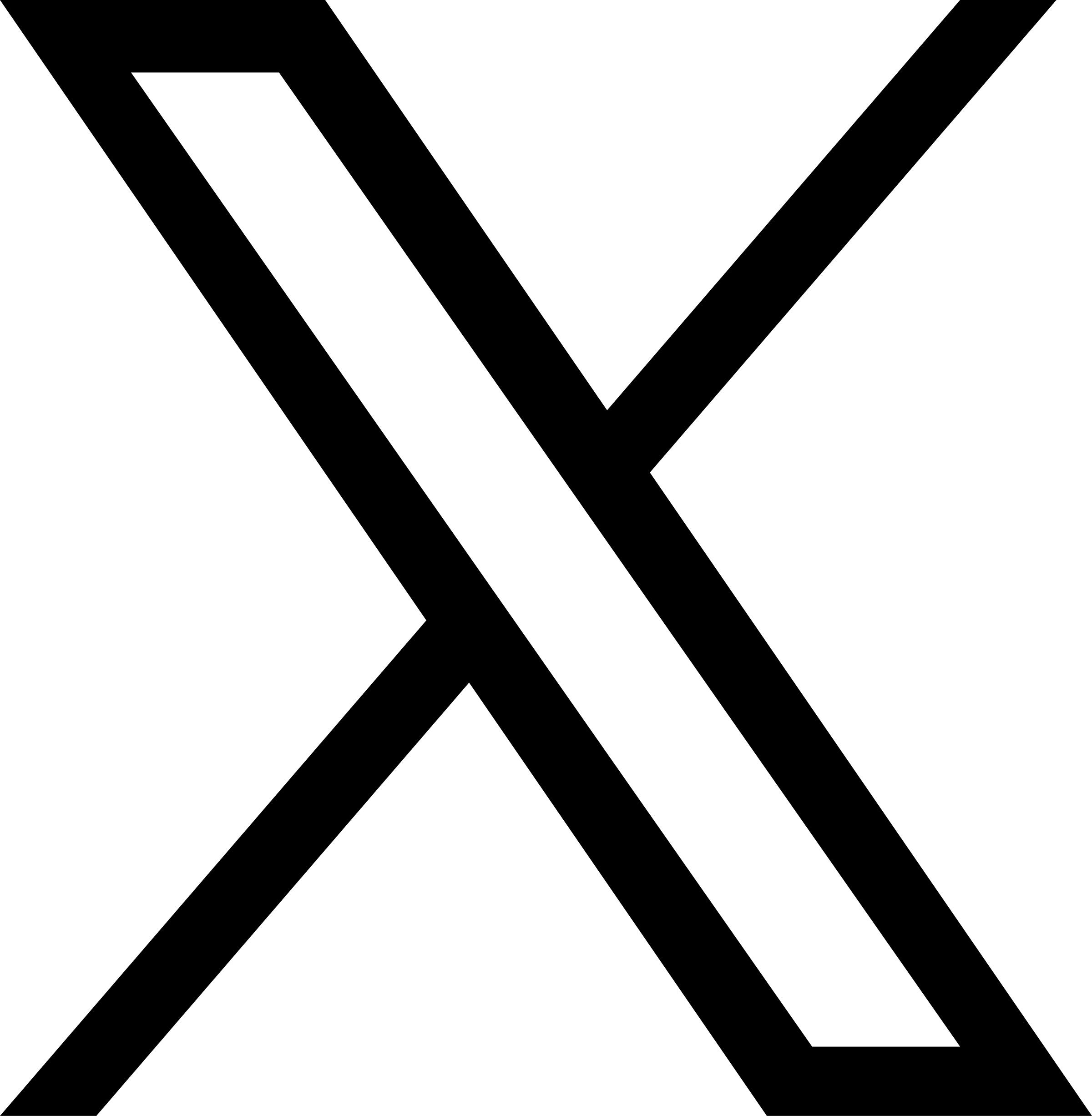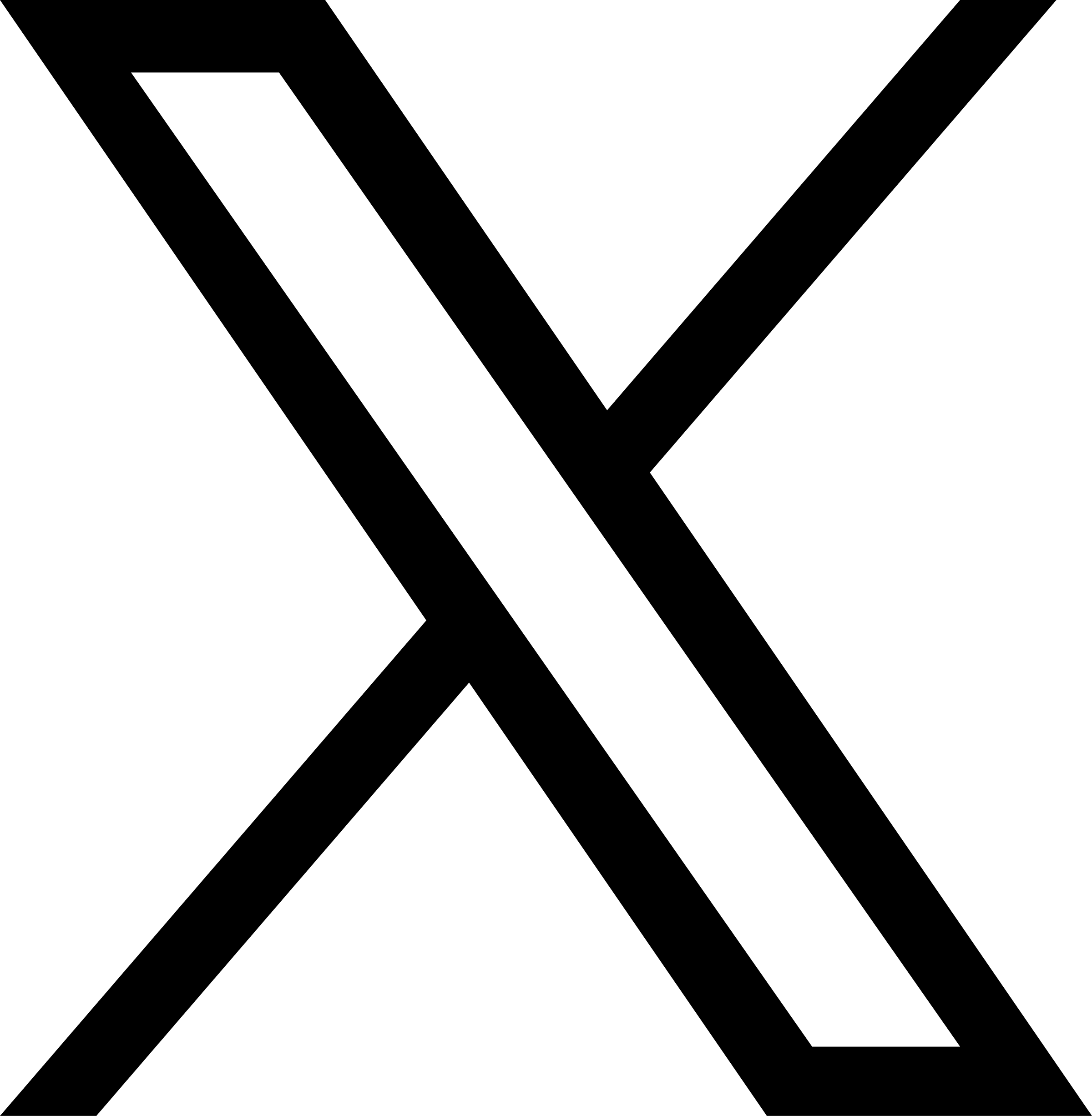就労移行支援事業所の対象者は?どんな人が利用できる?やさしく解説します
「自分は就労移行支援事業所の対象になるのか分からない」――そんな不安を抱える方へ。この記事では、制度の概要から対象者の特徴、利用までの流れまでを丁寧に解説しています。情報収集の第一歩としてご活用ください。

そもそも「就労移行支援」とは何か?
一般就労をサポートする福祉サービス
就労移行支援は、障がいや精神的な不調を抱える方が「一般企業での就職を目指すために必要な力」を身につけることを目的とした通所型の福祉サービスです。利用者は就労に向けた訓練やカウンセリング、履歴書の書き方指導などを受けながら、段階的に社会復帰を目指します。
この支援は単なる職業訓練ではなく、「働くこと」自体が大きな課題となる方に対して、生活リズムの改善や対人スキルの強化、自己理解の促進など、土台となる部分からサポートを行う点が特徴です。目の前の就職活動だけでなく、その後の定着や安定した働き方を見据えた長期的な支援が重視されています。
就労移行支援の利用には、行政の判断をもとに発行される「障害福祉サービス受給者証」が必要です。手帳の有無に関わらず、医師の意見書や診断書があれば利用できる場合もあります。制度としては全国共通のルールに基づいていますが、細かな条件や対応方針は自治体や事業所によって異なるため、事前の確認が推奨されます。
就労移行支援と他の支援制度の違い
障がいのある方が利用できる支援制度には、就労移行支援のほかにも「就労継続支援A型」「就労継続支援B型」などがあります。これらは、福祉的な就労の場を提供しながら一定の収入を得る仕組みです。就労移行支援が「一般就労を目指す前段階」であるのに対し、A型やB型は「福祉的な就労が目的」となっており、支援の方向性が異なります。
また、「就労定着支援」という制度も存在します。これは、一般企業に就職した後に職場に定着するまでの期間、安定した生活や人間関係を築くための支援を提供するものです。就労移行支援で培ったスキルを職場で活かしながら、悩みや不安を専門スタッフとともに解消していくための仕組みです。
このように、障がいのある方の「働き方」にはさまざまな選択肢が存在し、その中で就労移行支援は「企業就職」を目標にした明確なサポートを行う制度です。対象者や目的が異なる他制度と混同しないようにするためにも、自分の目標や現在の状況に合った制度を見極めることが大切です。
対象となる人の「年齢」や「就労の意欲」はどれくらい?
就労移行支援の対象となる年齢については、制度上、一定の範囲が設けられています。これは、一般就労を前提とした支援であることから、労働市場での採用機会や社会復帰の可能性を考慮して定められたものです。実際には、年齢の上限に達していても、ある条件を満たしていれば継続利用が可能となる場合もあり、年齢だけで一律に判断されることはありません。
年齢条件について正確に理解しておくことは、制度の利用を検討するうえで重要な要素です。就労移行支援は、就職を望むすべての人に開かれたサービスではなく、あくまで就労への準備や支援が必要な人を対象として設計されています。そのため、年齢が制度に適合していたとしても、他の条件との兼ね合いによっては利用が認められないこともあります。
一方で、制度上の基準を満たしていないように感じられても、自治体や事業所によって柔軟に判断されることもあり得ます。年齢だけで判断せず、まずは相談することが推奨されます。
「就職したい」という気持ちはどう判断される?
就労移行支援は「就職したい人」のための支援です。しかし、ここでいう「就職したい」という気持ちは、必ずしも明確な職業目標や職種が決まっていることを意味するものではありません。働きたいけれど何をすればよいか分からない、過去に挫折を経験して不安がある、という段階でも対象となる可能性はあります。
重要なのは、「自分の力で働けるようになりたい」という意志があるかどうかです。この意志は、初回相談や面談のなかで丁寧に確認されることが多く、必要に応じて支援者が一緒に整理を手伝うこともあります。就労意欲が不安定であっても、その背景に対する理解や支援体制が整っていれば、制度を活用することは十分可能です。
また、うつ病や不安障害、発達特性などの影響で働くことへの自信を持てない場合でも、意欲を引き出すためのサポートが存在します。具体的な職業が定まっていない状態での利用も想定されており、初期の段階から段階的に目標設定を進めていく支援が組まれています。
自ら「就職したい」と言えない状態でも、周囲の助けを得ながら意思形成をしていくことができるのが、就労移行支援の特徴の一つです。そのため、「自分に意欲があると言えるのか分からない」と感じている人でも、利用の検討をはじめてみる価値があります。
対象となる障害や疾患の種類
主に対象となる障害の例
就労移行支援は、障がいや疾患などによって働くことが難しい状況にある人に向けた制度です。利用対象となる障害の範囲は幅広く、精神障害、発達障害、知的障害、身体障害などが含まれています。具体的な病名や診断名に関係なく、「何らかの支援が必要である」と判断された場合に利用の可能性があります。
たとえば、精神障害にはうつ病や不安障害など、発達障害には自閉スペクトラム症や注意欠如・多動症などが該当します。知的障害や身体障害についても、それぞれ特性に応じた支援が用意されています。各障害ごとに課題や困難の内容が異なるため、個別の配慮やプログラム設計が行われることが一般的です。
特に精神疾患や発達特性を持つ方は、働くうえでのコミュニケーションや環境への適応に悩みを抱えることが多いため、就労に向けた支援が段階的に進められます。支援の目的は、「できないことを補う」のではなく、「その人らしく働く方法を見つける」ことにあります。
難病やグレーゾーンの人は利用できる?
障害者手帳を持っていない場合でも、医師の診断書や意見書があれば就労移行支援を利用できる可能性があります。これは、制度が障害の有無だけでなく、「日常生活や就労において支援が必要かどうか」を重視しているためです。
たとえば、難病に該当する疾患を持っている場合や、診断はついているが手帳の取得までは至っていないケースでも、就労に困難を抱えていると認められれば、支援の対象となることがあります。いわゆる「グレーゾーン」とされる状態であっても、制度上は柔軟に対応される場合があり、医師の意見や自治体の判断によって対象になることがあります。
また、現在は手帳を持っていなくても、支援を通じて必要な制度を整えていくという選択肢もあります。障害の有無を明確に証明することが難しい段階であっても、まずは相談をすることが出発点となります。
対応範囲は事業所ごとに違う
就労移行支援は全国に多くの事業所がありますが、すべての事業所がすべての障害に対応しているわけではありません。たとえば、精神障害に特化したプログラムを提供しているところもあれば、発達障害への支援に強みを持つところもあります。それぞれの事業所には支援体制や専門職の配置に違いがあり、自分の課題に合ったサポートを受けられるかどうかは大切なポイントになります。
見学や事前相談の際には、自分の状態や課題について率直に伝え、その事業所がどのような障害に対応しているのかを確認することが重要です。支援内容のカリキュラムだけでなく、職員の専門性や過去の支援実績なども判断材料となります。
LITALICOワークスやココルポートのように幅広い障害に対応する大手の支援事業所があり、各地域でメルディアトータルサポートのような地域密着型の事業所も存在しています。どの事業所が合っているかは、個人の状況によって異なるため、複数の事業所を比較検討することが推奨されます。
自分が対象かどうかの具体的な判断ポイント
制度上の対象者と、実際の利用者の違い
就労移行支援の制度では、対象者の条件としていくつかの基準が設けられていますが、実際の運用においては、必ずしもそれだけで利用できるとは限りません。たとえば、制度上の条件をすべて満たしていても、各事業所の受け入れ体制や支援の方針によっては、利用が難しいケースもあります。
一方で、明確な診断がない場合や、本人が対象かどうか不安に感じている段階であっても、支援の必要性が認められれば利用が進むこともあります。制度と実際の運用には一定の幅があり、判断のよりどころは自治体や支援機関の判断に委ねられている部分もあります。
こうした状況を踏まえると、「制度の条件に該当しているか」だけでなく、「自分の状況に対してどのような支援が必要か」を軸に考えることが重要です。
チェックすべきポイント
自分が就労移行支援の対象となるかを判断するためには、いくつかの視点から状況を整理する必要があります。以下のポイントは、相談時に問われることが多い内容です。
まずは、障がいや疾患の有無とその影響です。これは医療機関からの診断書や通院記録などがあれば整理しやすくなります。診断がない場合でも、働くうえでの困りごとが明確であれば、支援対象として見てもらえる可能性はあります。
次に、年齢に関する条件です。制度上の上限年齢が設定されているものの、利用開始時点での年齢や自治体の判断によっては例外が認められる場合もあります。
そして、「就職したい」という意志の有無です。はっきりとした職業目標がなくても、就労に向けた取り組みを始めたいという意思があれば対象になり得ます。気力や体調に不安がある場合でも、段階的に準備できるプログラムが存在するため、最初からすべてが整っている必要はありません。
地域によって支援内容や判断基準が異なることもあるため、同じ条件でも対応が異なるケースがある点にも注意が必要です。
対象か不安なときの対応方法
自分が就労移行支援の対象かどうか判断がつかない場合は、まず専門機関に相談することが最も確実な手段です。各市区町村の障害福祉課や、地域の相談支援事業所、ハローワークの障害者担当窓口では、制度の説明だけでなく、個別の状況に応じたアドバイスを受けることができます。
また、民間の就労移行支援事業所では、無料相談や体験利用を実施しているところも多くあります。たとえば、LITALICOワークスやココルポートなどは全国展開しており、地域に拠点を持つメルディアのような事業所も、初期相談から親身に対応していることで知られています。
体験利用を通じて自分の状態を客観的に捉えることができるため、「対象かどうか不明なまま踏み出すのが不安」という方にとっても、リスクの少ない一歩となります。制度を活用するうえで最も避けたいのは、「対象でないかもしれない」と思い込んで支援の機会を逃してしまうことです。
どんな支援が受けられるのか?利用の流れと内容
支援内容の具体例
就労移行支援事業所で提供される支援は、単なる職業訓練にとどまりません。利用者一人ひとりの課題や目標に合わせた個別プログラムが組まれ、日常生活の安定から職場での適応力向上まで、幅広い内容が網羅されています。
よくある支援のひとつが、ビジネスマナーや対人スキルのトレーニングです。あいさつや報告・連絡・相談といった基本的なコミュニケーションから、職場での人間関係に関する考え方まで、実践的なスキルを少しずつ習得できるよう構成されています。
また、履歴書や職務経歴書の作成指導、模擬面接などの就職活動支援も重要な支援項目です。自分の強みや働き方の希望を整理するための自己分析やキャリアカウンセリングも組み込まれており、単なる書類作成にとどまらず、「自分らしい働き方」を一緒に見つけていくことが可能です。
さらに、PCスキルや作業訓練など、実務に近い内容の訓練を行うこともあります。支援内容は事業所によって異なりますが、利用者のニーズや将来の就労先に応じて柔軟に設計される点が特徴です。
利用までの流れ
就労移行支援の利用は、いきなり始まるものではありません。まずは見学や相談を通じて、自分に合った事業所を選ぶところからスタートします。その後、行政への申請手続きを経て、正式な利用が始まる流れとなります。
最初のステップは、複数の事業所の中から候補を選び、実際に見学に行くことです。多くの事業所では、無料の体験利用や個別相談を受け付けており、支援内容や雰囲気を体感することができます。
利用を決めたあとは、市区町村の窓口にて「障害福祉サービス受給者証」の申請を行います。必要な書類や手続きについては、事業所側が丁寧にサポートしてくれることがほとんどです。受給者証が発行されると、正式な契約と利用開始へと進みます。
利用が始まってからは、個別支援計画に基づいてトレーニングがスタートします。支援スタッフと定期的に面談を行い、訓練の進捗や心身の状態に合わせて内容を調整していく仕組みです。無理のないペースで進めることができるため、就職に対して不安を感じている方にも取り組みやすい制度となっています。
支援実績のある代表的な事業所
就労移行支援は、全国で多くの事業所が展開されています。その中でも代表的な存在として知られているのが「メルディアトータルサポート」「LITALICOワークス」「ココルポート」です。
メルディアトータルサポートは、地域に根ざした支援を強みに持ち、発達障害や精神障害などさまざまな障害に対応したプログラムを提供しています。ひとりひとりの課題や個性を理解し、職場での安定した定着を見据えた支援を行っている点が特徴です。
LITALICOワークスは、全国に多くの事業所を展開しており、幅広い年齢層・障害種別に対応しています。個別支援計画の質が高く、利用者との密なコミュニケーションを重視した支援が特長です。
ココルポートは、体験利用制度やアフターフォローが充実しており、就職後のサポートも視野に入れた長期的な支援を展開しています。支援体制が整っているため、初めて制度を利用する方にも安心感があります。
これらの事業所はそれぞれに強みがあり、自分に合った支援スタイルを選ぶことで、就職に向けた大きな一歩を踏み出すことが可能になります。
対象者かどうかで迷ったら、まずは一歩踏み出しましょう
就労移行支援は、「働きたい」という気持ちに寄り添いながら、一人ひとりのペースで前に進める支援制度です。年齢や障がいの種類、明確な職業目標の有無にかかわらず、就労に向けた準備を始めたいと思ったときが行動のタイミングです。
自分が対象になるのか判断できない場合でも、相談を通じて支援の可能性を確認できます。迷いや不安がある方こそ、まずは情報を集めて、自分に合った支援を知ることが大切です。
もし「自分も対象かもしれない」と感じたら、地域に根ざした支援で実績のあるメルディアトータルサポートにご相談ください。あなたに合ったステップを、一緒に見つけることができます。
初回相談や見学も受付中です。詳しくは公式サイトをご覧ください。公式サイトはこちらから→ https://mlda.jp/mtsinquiry/