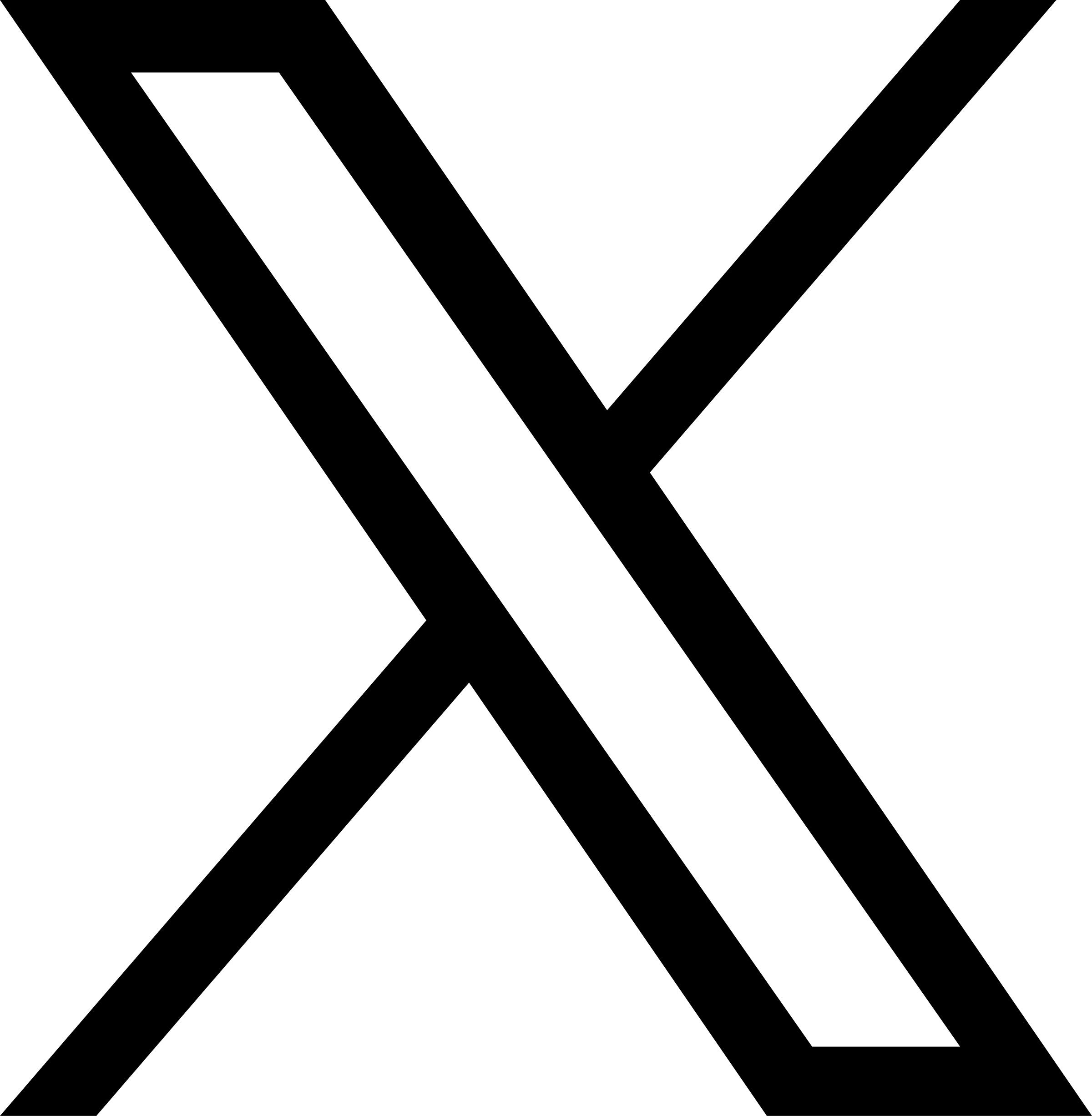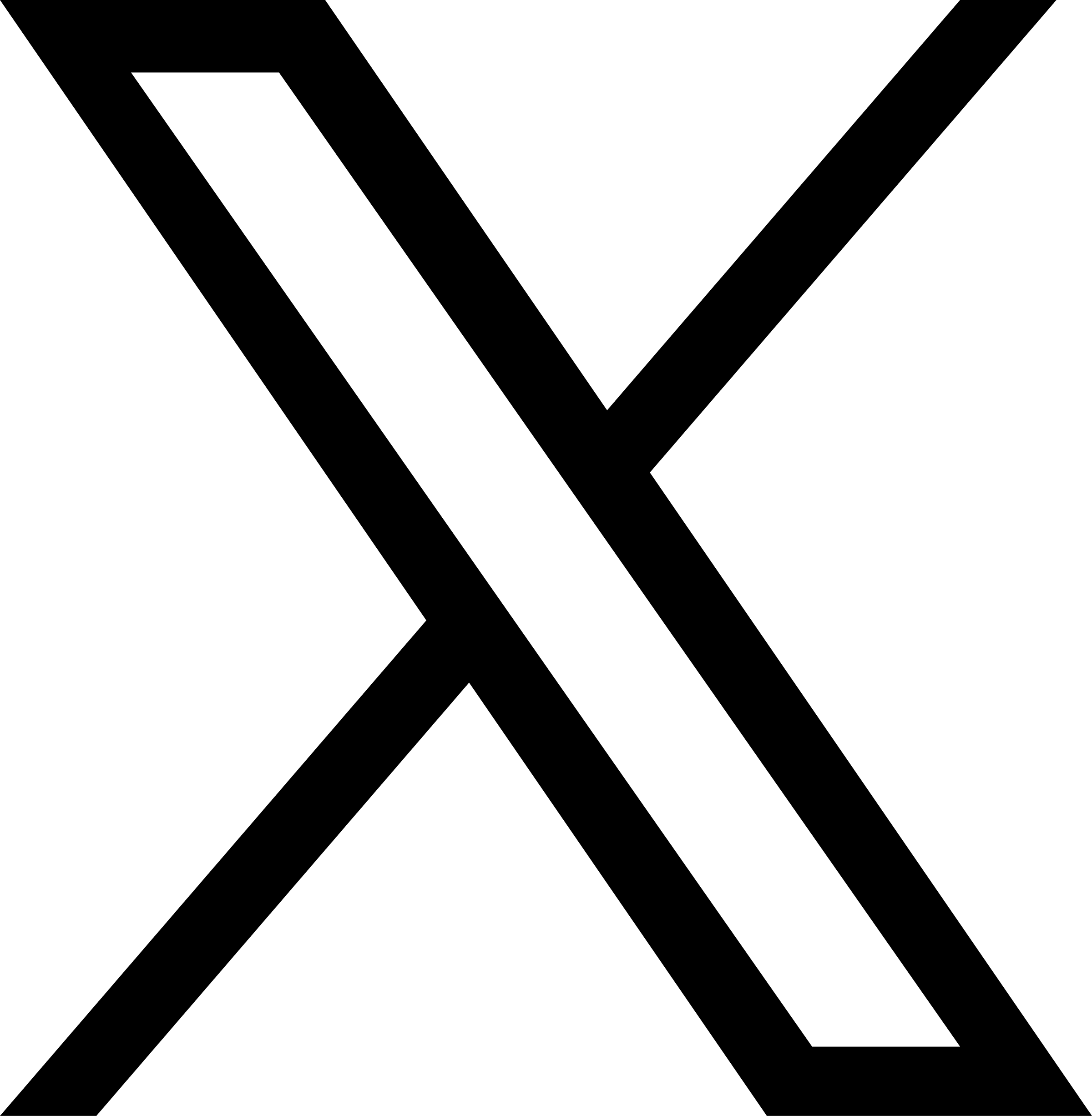就労移行支援事業所の数はどれくらい?自分にあった事業所の選び方を徹底解説
「働きたい」という気持ちを形にするためには、自分に合った環境や支援を見つけることが重要です。全国に数多くある就労移行支援事業所は、利用条件やサポート内容も多岐にわたります。本記事では、事業所の数や役割の解説に加え、他の支援制度との違いや事業所選びの視点も丁寧に解説。支援を受ける際の判断材料として活用いただけるよう、分かりやすくまとめています。

全国に広がる就労移行支援事業所の数はどれくらい?数が多いことの背景は?
就労移行支援事業所は、働くことに不安を抱えている人が、自分らしく社会とつながるための制度的な支援機関です。障害のある人が地域社会で尊厳を持って生活し、就職という形で自立を目指すためのサポートが提供されています。この制度は、単なる職業訓練を超えて、日常生活の安定から職場での適応までを含めたトータルな支援を行う点に特徴があります。就労移行支援事業所は2023年時点で、全国には3,595ヶ所存在します 。この数は、年々増加しており、働くことを希望する障害を持つ人々へのニーズが高まっています。
制度の背景には、誰もが社会の一員として活躍できる環境を整えるという国の基本方針があり、地域ごとにその実践が進められています。就労移行支援はその一環として位置づけられ、障害があることで働くことをあきらめていた人にも、新しい道を切り拓く機会を提供しています。
事業所数の変化が示す社会的ニーズ
事業所の数が増えてきている背景には、障害のある人への社会的理解の広がりと、就労支援を求める声の高まりがあります。以前に比べ、精神疾患や発達障害を持つ方が職場に適応しやすいような環境整備が進んでいることも、利用者の増加に拍車をかけています。
また、雇用する側の企業も、障害者雇用への意識が高まりつつある中で、就労移行支援事業所と連携し、マッチングの機会を得ることに価値を感じています。事業所の数が多いことは、利用者にとって選択肢が広がることを意味し、自分に合ったサポートを受けるチャンスが増えるという大きな利点があります。
こうした背景から、就労移行支援事業所は単なる福祉施設ではなく、地域社会と連携した重要な就労支援インフラとしてその存在価値を高めています。
就労移行支援を受けられる人の条件とは
支援を受けるための基本的な対象は?
就労移行支援サービスは、すべての人が利用できるわけではありません。サービスの提供対象者は法律に基づいて定められており、一定の条件を満たしていることが求められます。利用の検討にあたっては、自身がこの条件に該当するかを把握することが重要です。
まず、年齢については原則として18歳以上65歳未満であることが前提となります。この範囲内であれば、就労に向けた意欲があり、支援を受けながら一般就労を目指す人が対象になります。
また、支援の対象となる障害の範囲も広く、精神障害、発達障害、知的障害、身体障害のほか、特定の難病に該当する人も対象に含まれています。どの障害が対象になるかについては、障害者総合支援法の枠組みをもとに判断されます。
手帳の有無は必須条件ではない
就労移行支援を利用するにあたり、「障害者手帳の取得が必要なのではないか」と不安を抱く方も少なくありません。しかし実際には、障害者手帳を持っていなくても、医師による診断書があり、障害の状態が確認できる場合には、サービスの利用が認められることがあります。
この判断は自治体ごとに異なることもありますが、重要なのは「働くことに困難があり、支援が必要である」と認められるかどうかです。手帳の有無にこだわらず、自分の状態や就労への意欲を正直に伝えることが、利用に向けた第一歩となります。
通院・治療を継続していることは重要性
医師の診断があるだけでなく、継続的な通院や治療を行っていることも条件のひとつに挙げられる場合があります。これは、症状の安定や体調管理が就労支援の土台となるためです。
就労移行支援事業所では、通所のペースやプログラム内容が個々の体調や生活状況に合わせて調整されます。そのため、現在の医療的な状況や支援の必要度を医療機関と共有しながら進めることが重要です。
支援のスタート時には、主治医の意見書を求められるケースもあります。これは、医療的な視点から見て就労支援の利用が適しているかを判断するためのものであり、利用者にとっても安心して支援を受けるためのプロセスとなります。
就職への意欲が明確であること
就労移行支援は、将来的に一般企業での就職を目指す人のためのサービスです。そのため、「働きたい」という気持ちがあることが最も基本的な利用条件のひとつとされています。
この意欲は、現時点でのスキルや体調に左右されるものではなく、将来的に働くことを目指しているかどうかという姿勢の部分です。「自分にできることから始めたい」「少しずつ社会とつながっていきたい」という思いがあれば、それは立派な意欲として捉えられます。
就職の目標がまだ具体的でない場合でも、支援の中で自己理解を深め、適職を探していく過程が用意されているため、不安を抱えていても利用は可能です。
他の就労支援サービスとの違いを知る
就労移行支援は「就職」がゴール
就労移行支援は、一般企業での就職を目標とした支援サービスです。これは、他の就労支援サービスと大きく異なる点です。支援内容は、職業訓練や生活習慣の見直し、ビジネスマナーの習得、履歴書作成支援、模擬面接など、就職に直結する実践的な内容が中心です。
他にも働くことに関する支援制度は複数存在しますが、それぞれに目的と役割が異なります。就労移行支援は、「今はまだ働ける自信がないけれど、将来は一般企業で働きたい」と考えている人にとって、準備期間として活用できる点が特徴的です。
就労継続支援との違いを理解する
就労支援サービスの中には、「就労継続支援A型・B型」という制度もあります。これらは就労移行支援と混同されがちですが、目的が異なります。
就労継続支援A型は、雇用契約を結びながら働く場を提供するものです。働きながら生活リズムを整えたり、作業能力を高めたりすることが目的となります。一方でB型は、雇用契約を結ばず、より柔軟な形で作業や訓練を行うスタイルで、体調に波がある方や長時間働くことが難しい方に適しています。
これらの支援は、長期的に安定して作業を継続することが重視されます。それに対して就労移行支援は、「自立した就職」を目指すため、利用期間が原則2年と定められており、卒業を前提とした支援計画が立てられるのが大きな違いです。
ハローワークとの違いも押さえておく
ハローワークもまた、就職をサポートする公的機関ですが、就労移行支援とは役割が異なります。ハローワークでは主に、求人の紹介や職業相談、職業訓練校の案内などが提供されます。
しかし、ハローワークでは日々の通所や生活支援、就労準備のためのトレーニングなどは行われません。ある程度の自己管理能力や就労準備ができている人向けのサービスであり、手厚い個別支援を必要とする段階の方にはややハードルが高く感じられることもあります。
就労移行支援は、こうしたハローワークなどの支援と並行して利用することも可能です。段階を経ながら、将来の就職に向けてスムーズに準備を進める手段のひとつとして位置づけられています。
支援内容の深さと伴走力が違いを生む
就労移行支援では、ただスキルを学ぶだけではなく、「本人の状態に合わせた支援設計」が行われます。個別支援計画が立てられ、支援員が伴走する形で進められる点が大きな強みです。
たとえば、生活リズムを整えることから始める支援もあれば、通所の頻度を段階的に増やすケースもあります。また、実習や職場体験といったリアルな環境での経験を通じて、自信を育てていく機会も豊富に用意されています。
こうしたきめ細やかな対応により、ただ就職するだけでなく「職場に定着する力」を養うことが可能になります。他の支援と比較しても、就労移行支援のサービスは「長く安定して働くための土台づくり」に特化している点が特徴です。
就労移行支援事業所の選び方と成功に近づく判断基準
事業所選びが就職成功のカギになる
就労移行支援は、目的や支援内容が共通していても、各事業所によって提供するプログラムやサポート体制に違いがあります。だからこそ、自分の状況や目的に合った事業所を選ぶことが、就職成功に直結します。ただ「通いやすいから」や「なんとなく良さそう」といった理由で選んでしまうと、自分に合わない支援内容で成果を得られにくくなる場合もあります。失敗を避けるためにも、いくつかの視点を持って選ぶことが大切です。
アクセスのしやすさと通所の継続性
最初に確認したいのが事業所までのアクセスです。どれだけ良い支援内容があっても、通うことが負担になれば継続が難しくなります。自宅や最寄り駅からの距離、天候の影響を受けにくいかどうかなどもチェックポイントです。無理のない通所ができる環境が、安定した訓練や支援を受けるための土台になります。
また、生活リズムを整える段階から始める方にとっては、通所そのものがトレーニングの一環です。無理なく通える立地にあるかどうかを最優先の判断材料とすることで、就職に向けた土台作りがより確かなものになります。
プログラムの内容と柔軟性
次に確認すべきなのが、提供されているプログラムの内容です。就労移行支援は、事業所によってプログラムの構成や重点が異なります。たとえば、PCスキルの習得を重視している事業所、対人関係のトレーニングを強化している事業所、企業実習の機会が豊富な事業所などがあります。
また、プログラムの柔軟性も重要です。一人ひとりの特性や目標に合わせて、支援計画をカスタマイズできるかどうかを確認しましょう。決まった内容だけを一律に提供している事業所では、個々の課題に応じた成長が難しくなることがあります。個別性を重視した支援体制があるかどうかが、事業所選びの質を左右します。
スタッフ体制と支援の質
スタッフの構成や支援体制も、選定時の重要なポイントです。職業指導員、就労支援員、生活支援員、精神保健福祉士など、多職種が連携して支援しているかどうかをチェックしてください。相談したいことに応じて適切なサポートが受けられる体制が整っていることは、安心感につながります。
また、面談の頻度やフィードバックの丁寧さも注目したい要素です。小さな課題や不安に対しても、こまめに対応してくれる事業所は、利用者との信頼関係を大切にしている可能性が高く、結果的に就労につながりやすくなります。
定着支援と就職後のフォロー
事業所を選ぶときは、「就職できるかどうか」だけでなく、「働き続けられるかどうか」にも着目しましょう。就職後も継続的にサポートしてくれる体制があるか、定着支援の内容や期間についても確認することが大切です。
たとえば、就職後に定期的なフォロー面談を実施してくれる、勤務先との連携を行ってくれるといった支援があると、職場での不安やトラブルを早期に解消でき、長期的な就労につながりやすくなります。
全国に広がる支援のネットワークと地域格差
就労移行支援の制度は全国共通
就労移行支援は、国の制度に基づいて提供されている福祉サービスです。そのため、制度の内容や利用条件、支援の基本的な枠組みは全国で統一されています。これは、住んでいる地域によって受けられる支援内容が極端に異ならないよう配慮されているからです。利用者が制度の違いで不利益を受けることがないよう、制度面では一定の公平性が保たれています。
しかし、制度が全国共通であっても、実際の運営は各事業所ごとに異なります。地域の特性や利用者の傾向に合わせて、支援のアプローチやプログラム内容が調整されているため、住んでいる地域によってサービスの質や幅に違いが生じることがあります。
地域によって偏りがある事業所の分布
就労移行支援事業所は全国に設置されていますが、その分布には明らかな偏りが存在します。都市部には事業所が集中しやすく、選択肢も多いため、利用者が自分に合った事業所を見つけやすい傾向にあります。特に、駅近の利便性やビル設備の充実、実習先企業のバリエーションなど、都市部ならではの強みを持つ事業所が目立ちます。
一方で、地方や郊外の地域では、事業所の数そのものが少ない場合があり、選択肢が限られることがあります。アクセスに時間がかかる、実習先が限られる、専門スタッフの数が少ないといった課題に直面することもあり、利用者にとっては環境面でのハードルとなる可能性があります。
地域格差にどう対応すべきか
このような地域格差に対して、どのように対応すべきかを考えることは重要です。まず、通所にかかる距離や時間だけで判断せず、支援内容やサポート体制を優先して検討することが大切です。多少距離があっても、支援が自分に合っていると感じられる事業所を選ぶことで、結果的に就職につながる可能性が高まります。
また、現在では多くの事業所がオンライン支援を一部取り入れています。遠隔での相談や学習支援、体調管理に関するアドバイスなど、ICTを活用した柔軟な支援を提供しているところもあるため、地域に事業所が少ない場合でも、対応可能な選択肢が広がりつつあります。
自治体ごとの支援体制にも注目
就労移行支援は、事業所単体ではなく、自治体の福祉窓口との連携も重要なポイントです。自治体によっては、事業所との連携が強固で相談体制が整っている場合があり、スムーズな手続きや利用開始が可能になるケースもあります。反対に、支援の周知が不十分であったり、手続きに時間を要する地域では、利用者が不安を抱えやすくなることもあるため、自治体の支援体制や担当窓口の対応状況も把握しておくことが有効です。
事業所を探す際は、自治体の福祉課や障害福祉窓口に相談することで、地域内で利用可能な事業所の情報や、自分の状況に合ったサービスの案内を受けることができます。複数の事業所を比較したうえで、自分の目的や希望にもっとも合った場所を選ぶ姿勢が求められます。
就労移行支援事業所は自分にあった場所を見つけよう
全国に多くの就労移行支援事業所が存在する中で、自分に合った支援を見つけることは容易ではありません。サービスの内容、サポートの質、スタッフとの相性など、さまざまな要素を比較・検討することが必要です。
メルディアトータルサポートは「アクセスの良さ」「特性に合わせた」「一貫サポート」などおすすめの理由が揃ってる
メルディアトータルサポートの大きな特徴のひとつは、駅直結という通いやすい立地にあります。上野御徒町駅・仲御徒町駅から徒歩1分圏内というアクセスの良さは、安定した通所習慣をつくるうえで非常に重要な要素です。通うこと自体にストレスが少なく、生活リズムを整えやすいため、支援を受ける環境として非常に整っています。体調面に不安を感じている方や、毎日外出する習慣をつけたい方にとっても安心感のある立地です。
メルディアトータルサポートでは、利用者それぞれの特性に応じた個別プログラムを用意しています。就職に向けて必要なスキルは人によって異なります。コミュニケーションが課題の人もいれば、生活リズムの安定が最優先の人もいます。メルディアでは、PC操作や実務系スキルの習得に加えて、ジョブトレーニング、ビジネスマナー、グループワークといった多角的な訓練が提供され、段階的に就職に必要な力を養うことができます。柔軟なプログラム構成が、就労への自信につながります。
単に就職先を見つけるだけでなく、「就職後に長く働き続けること」まで見据えた支援を提供している点も、メルディアの大きな強みです。就労準備の段階では、性格傾向や興味関心を把握するアセスメントを通して自己理解を深め、それに基づいて職種や職場環境の希望を具体化していきます。
また、就職活動の際には、履歴書作成や面接練習だけでなく、実際の企業とのマッチングや職場見学もサポートします。さらに、就職後も定期的なフォロー面談を実施し、環境の変化に適応できるよう支援が継続されます。この一貫したサポート体制が、「続ける働き方」を可能にしています。
これまで就職に対して不安や戸惑いを抱いていた方も、正しい支援と環境があれば、新しい一歩を踏み出すことができます。メルディアトータルサポートは、そんなあなたの「はたらきたい」という想いを受け止め、実現に向けて伴走するパートナーです。無料相談や見学は随時受付中なので、まずは一度、実際の支援内容や雰囲気を体験してみてください。
あなたの就職への一歩を、メルディアトータルサポートが全力で応援します。
初回相談や見学も受付中です。詳しくは公式サイトをご覧ください。公式サイトはこちらから→ https://mlda.jp/mtsinquiry/